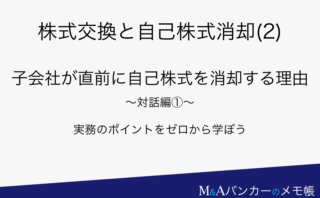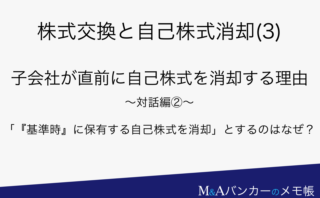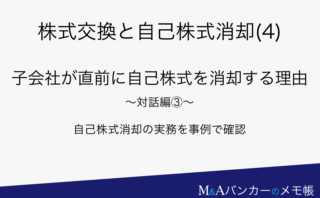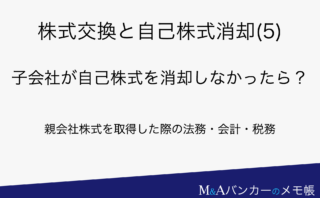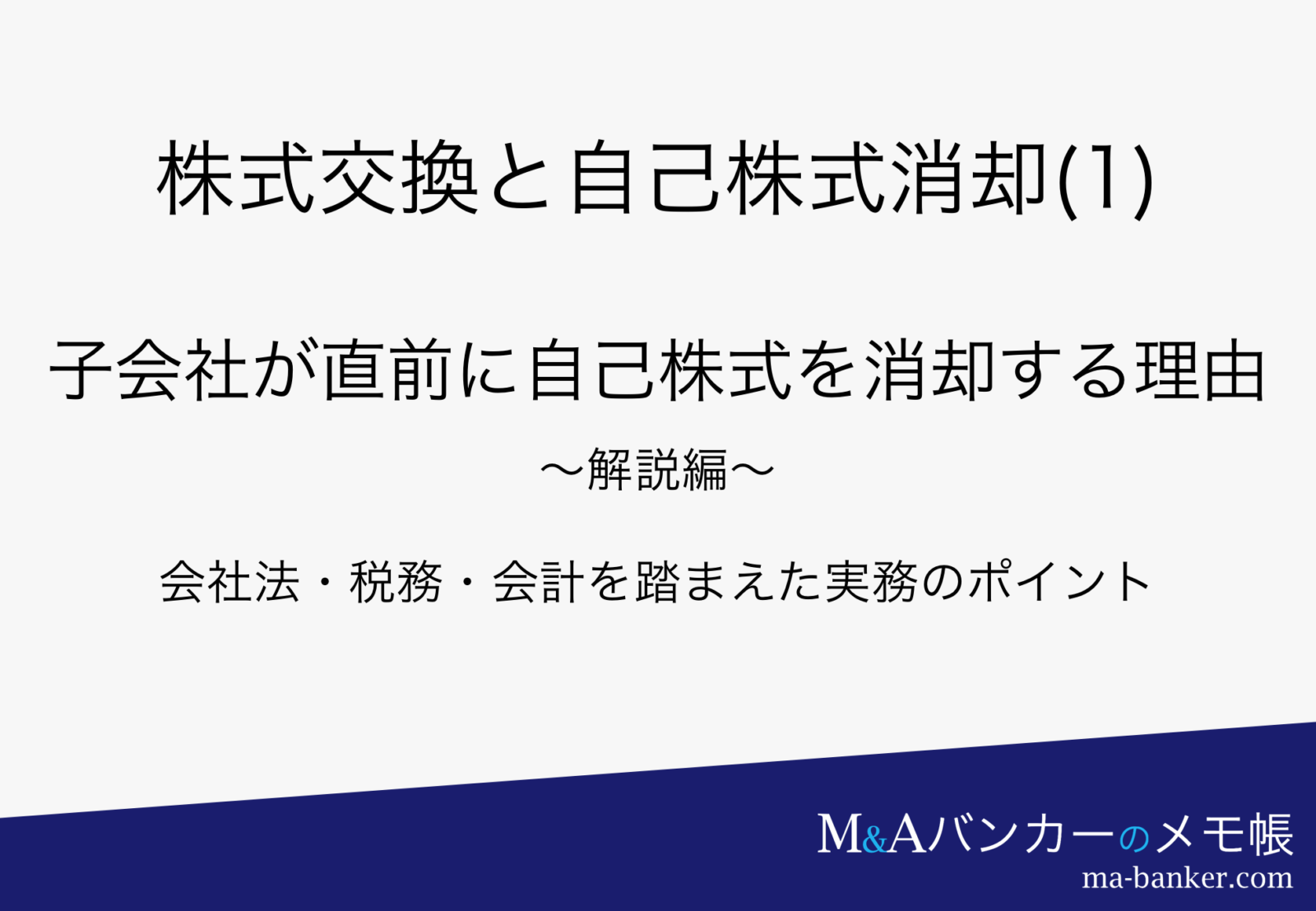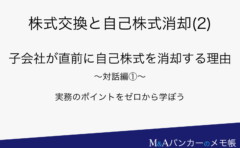上場会社を完全子会社化しようとする場合、対価の種類によって用いられる手法が変わってきます。具体的には、
- 現金対価:TOB+スクイーズアウト
- 株式対価:(TOB)+株式交換
といった実務慣行があります。
現金対価の場合にはTOBを経ないことはほぼありませんが、株式対価の場合にはTOBを経ずに子会社でない会社を株式交換で完全子会社化することもあります(経営統合という位置づけだったり、親会社になる会社が現金を使いたくない場合にTOBを経ないこともあります)。
事例としては、現金対価のTOB+スクイーズアウトによる完全子会社化の方が多いようですが、株式交換による完全子会社化も時期を問わず一定の件数がありそうです。
(参考記事)

上記の通り、以前、株式交換の入門記事をまとめましたが、最近、株式交換と自己株式消却について照会を受けることがありました。なので、改めて、株式交換に際して効力発生の直前に子会社側が自己株式を消却する実務について法規制を含めてその理由を見ていきたいと思います。
記事の構成としては、今回の解説編と次回以降の対話編にわけております。
解説編ではポイント・結論を簡潔にまとめ、対話編ではいつもの先輩・後輩の対話形式で実務を確認していく流れとなっております。
解説編
株式交換において子会社が保有する自己株式を消却するのは、会社法、会計及び税務が複雑に関連しておりますので、それぞれの側面で見ていきたいと思います。
会社法のポイント
親会社株式保有禁止の原則の観点
- 合併の消滅会社と異なり、株式交換の子会社が保有する自己株式には組織再編の対価が割当・交付される(会社法749条1項三号括弧書、会社法768条1項三号)
- ゆえに、株式交換では子会社が保有する自己株式に対して何ら手当てをしないと、効力発生日に親会社株式が割当・交付される
- 会社法上、原則として子会社は親会社株式を保有できず(会社法135条2項五号、会社法施行規則23条二号)、保有してしまった場合には相当の期間内に処分しなければらないない(会社法135条3項)
買取請求に伴う自己株式増加の観点
- 株式交換に反対する株主が買取請求権を行使してきた場合、完全子会社サイドでは株式交換の効力発生日にその買取請求の効力が発生し、取得した株式は自己株式になる(会社法785条1項)
- すなわち、効力発生日の前日までに買取請求された分だけ自己株式の数が増える
- 従って、消却する自己株式の数を「効力発生の直前時に保有する自己株式数」と定義づけ、株式数の絶対値は定めないように留意する必要がある
会社法の結論
会社法の観点では、子会社が自己株式を消却せず親会社株式が割当・交付されてしまっても、その後適宜処分していけば差し支えない。
税務のポイント
税務上の自己株式の簿価の観点
- 税務上、自己株式の簿価はゼロであり、バランスシートに記載されている会計上の自己株式の金額と関係はない
- ゆえに、自己株式に親会社株式が割り当てられた場合、簿価ゼロの親会社株式を保有することになる
- その簿価ゼロの親会社株式を外部へ売却した場合、その簿価全額が益金に算入されるため税務負担が発生する
連結納税・グループ法人税制を踏まえた税務の結論
- かつては簿価ゼロの親会社株式の合理的な処分方法は限られていたが、現在は連結納税・グループ法人税制の適用により、簿価ゼロの親会社株式を親会社へ譲渡または現物配当することで実質的に無税で処理することができるようになった
- 従って、税務上も自己株式を残してしまっても合理的に処理できるようになった
会計のポイント
子会社の観点
- 会計上は株式交換に伴い、自己株式に親会社株式を割り当てられた際に、自己株式の簿価を親会社株式の簿価とはできない
- 代わりに、親会社株式を時価で受け入れたとして会計処理する必要がある(ASBJ:企業結合会計等適用指針238-3)
- 自己株式の簿価と親会社株式の時価との差額は普通の自己株式の処分と同じくその他資本剰余金の増減とする
- すなわち、会計上の処理はいわゆる「株式のみが割当・交付された一般株主」のように簿価引き継ぎとできないことに留意が必要
親会社の観点
- 単体:自己株式の消却の有無によって、増加する新株の数が異なるため、株主資本の増加額も異なる(親会社による自己株式代用処分でも処分される自己株式数が増加)
- 連結:自己株式の消却の有無によらず、発生する「のれん」及びできあがりの株主資本の金額(純額)は不変
会計の結論
会計の観点では、自己株式の消却の有無で主に単体上のインパクトは異なるが、世間的に実質的に重視されている連結の処理は不変であり、消却の有無が重要な差異となることはなさそう
実務上の煩雑さ・慣行のポイント
それでも、上場会社が関与する実務においては、自己株式の消却をしないケースはほぼ存在しない。
その理由としては次のような理由によるものと推察
- いずれ処分しなければならない親会社株式を敢えて発生させる必要性は乏しい
- そもそも処分という実務上の手間がかかる
- 税務上、実質無税で処理できるといっても現物配当のための剰余金が必要であったりする
- 株式交換案件で起用するFAや会計士等のアドバイザーが「過去事例をみても他社も基本的に自己株式は直前に消却している」とアドバイスするため、それでも残したいと思う会社は少ない
個人的な経験としても、株式交換の親会社側のFAとして起用された場合には子会社側のFAに自己株式の消却を依頼します(基本的にその依頼を断られることはありません)。
また、逆に子会社側のFAとして起用された際には、株式交換の親会社側の他のFAから消却をお願いされ、それを断る合理的な理由も乏しいため、親子のいずれであっても関与した案件は全て直前に消却となっております。
(次回の対話編に続きます)
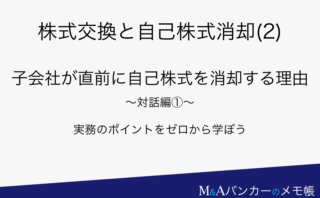
関連する連載記事(全5回)
https://ma-banker.com/exchange-of-shares-and-treasury-stock_1