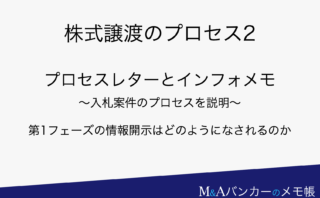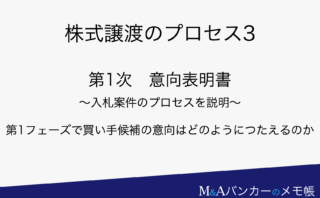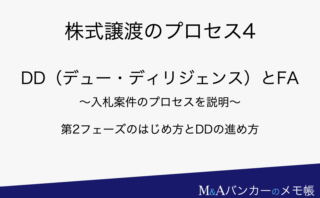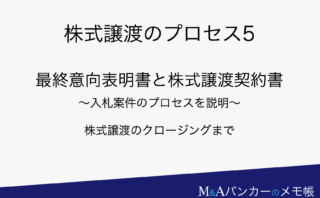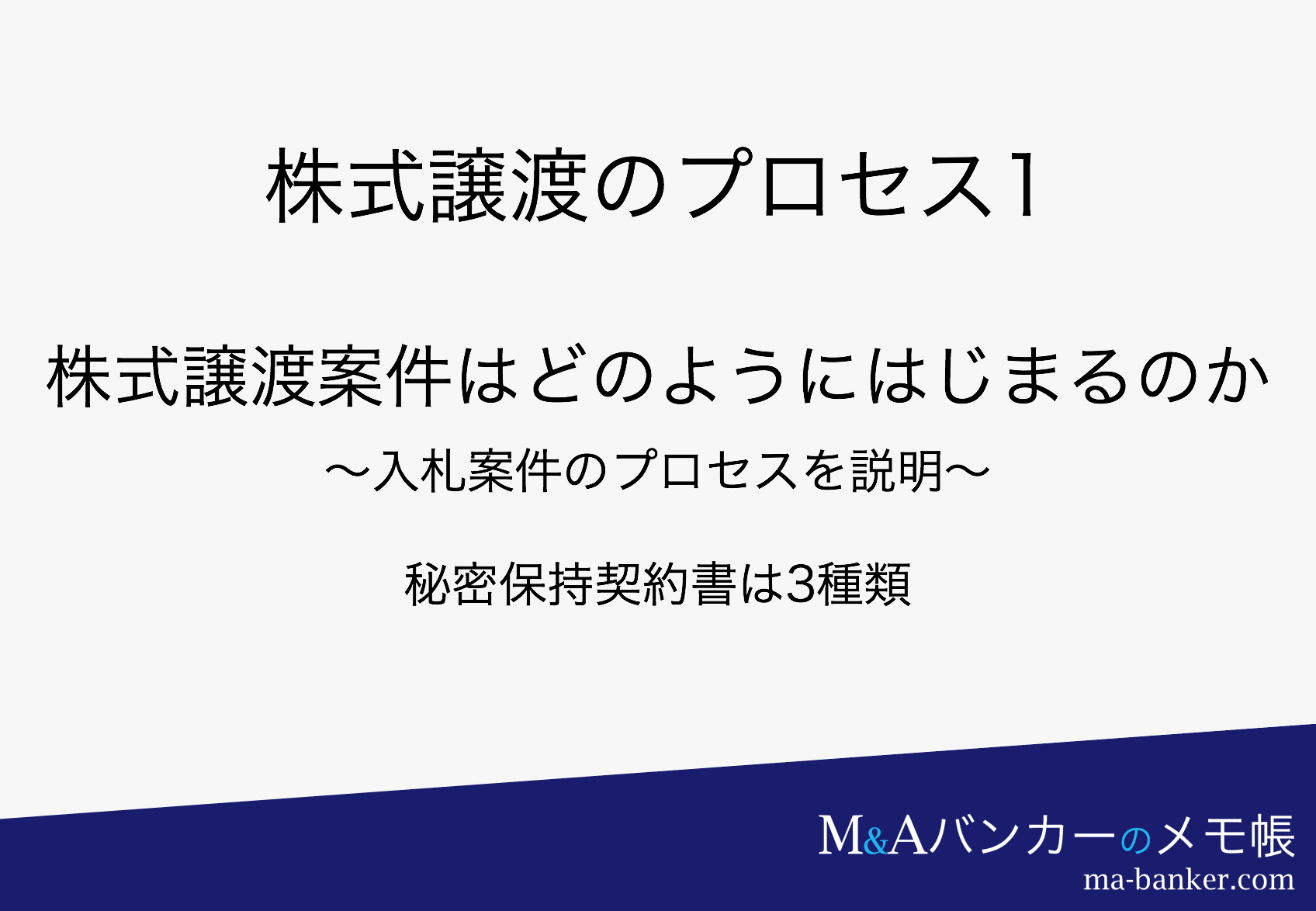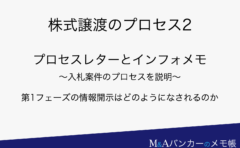今回からしばらく株式譲渡案件のプロセスについて説明してみようと思います。
M&A案件の進め方は、法規制や会計税務のように正解があるわけではなく、実務においては各案件ごとに個別の事情を勘案してプロセスを進めていくことになります。
とはいえ、一般的な「型」を知っておくのは実務において進め方を検討する際に有用かなと思いますので、記事にしてみました。
まず、一般的な入札案件の株式譲渡案件の一巡は次のような流れになると思います。
- 第1フェーズ
- ティーザーの配布と入札参加の決定
- アドバイザー(FA)、弁護士・会計士・税理士等専門家の起用
- 秘密保持契約書の締結
- 入札案内書(プロセスレター)、インフォメーションメモランダムの配布
- 第1次意向表明書の提出
- 第2フェーズ
このようなプロセス図はM&Aの解説書等にも記載されていますし、証券会社等のFA提案書にもこのようなプロセスの流れを簡単に説明したペーパーをつけることが多いです。
フェーズを分けた意味は?
プロセスは大きく分けて第1フェーズと第2フェーズに区別されます。
- 第1フェーズ
- 資料開示が限定的になる代わりに買手も法的拘束力のないオファーを提示
- 第2フェーズ
- デュー・ディリジェンス(DD)を実施するため資料開示の範囲は拡がり、それを踏まえた買手のオファーも法的拘束力のあるものになる
という大きな流れがあります。
法的拘束力のありなしでフェーズを分けるというイメージです。
これ以降では、各プロセスの場面で、
- FAとしてどのようなことを考えておくべきなのか
- それぞれのプロセスで登場する書類の記載内容の詳細
を見ていきたいと思います。
※入札案件の規模によっては、フェーズをさらに分けて、第3フェーズまで実施することもありますが、一般的にはフェーズを2段階に分けるケースが多いかと思いますので、ここでは2段階のケースを想定して説明していきます。
株式譲渡案件の始まり方:売手と買手のどちらが案件をはじめるのか?
株式譲渡案件の始まり方は、本当にいろいろなパターンがあって、一概にどうだということは言いづらいのですが、大きく分けると
- 売手が売却意志を決めていて買手を募るケース(売手主導のケース)
- 買手が売手に売却意向を探るケース(買手主導のケース)
の2つに分かれると思います。
売手主導のケース
ファンド案件や売却を決めた事業会社
まず、売手主導のケースとは、例を挙げると、ファンドの売り案件で「売却」ということは決まっていて、あとはどれだけ高値で売れるかということを追求するような場合です。
また、事業会社による売却案件であってもノンコアや不採算の事業であって「売ること」が決まっている場合もあります。
そのような場合には、一般的に入札形式になることとが多いです。
特に、ファンドは売却の際に相見積もりをとることが内規で決められていたり、事業会社であっても取締役の善管注意義務を果たすために入札を選ぶ傾向にあります。
ティーザーとは
売手が入札形式で売却プロセスをはじめようと考えた場合、売手の起用したFAを使って、買手候補となりそうな会社の興味度合いをはかることがあります。
そのような場合、売手のFAが「ティーザー」と呼ばれる対象会社の概要をA4用紙1枚程度にまとめた紙面を持ち回ることがあります。
ティーザーには対象会社の社名を書かずに、ノンネームで打診するケースの方が多いと思います。
といいますのも、買収意向が分からない会社に対して、対象会社の名前を認識させるのは一般的には得策ではないからです。
買手主導のケース
一方で、買手が主導的に案件化させようと動くケースもあります。
売ってください! → 売りません
買手主導の場合、売手が売るつもりがあるかどうかわからない会社を
「売ってください!」
と頼むことになりますので、売手に売る気がなく、そもそもM&Aのプロセスが始まらないケースがほとんどです(FA業界では「お買い物案件につきあう」と言われ・・・買手がM&Aをやると決め、買収テーマを設定し、ロングリストからショートリストに絞り込み、いざ売手に打診してみたら玉砕、なんて話はそこら辺にあります)。
売ってもらえないのは良い会社だから
売手主導の場合は、ノンコアだったり不採算の会社を売ろうということが多いですが、買手主導の場合、買収ターゲットの会社は良い会社の場合が多いです。
そうなると、必然的に売手としては基本的にそういう良い会社を手放すことは
「考えていません」
というのがほとんどになってしまうわけです。
もしかしたら金額次第では・・・
買手主導のケースは案件化することは多くはないのですが、場合によっては
「条件次第では売っても良いかもしれない」
と考える売手もいます。
特に、売手のなじみの証券会社が買手を連れてきた場合には、
「検討してみる価値があるかもな」
と思っていただけることもありますので、買手としては、良いネットワークを持っているFAと話をすべきです。
なお、売るかどうかは確定していないけれども、とりあえず話だけは聞いてみようかという感じの場合は、大抵相対形式でのプロセスになります。
といいますのも、売るかどうか確定していない以上、入札形式にして情報を拡散するのは得策ではないからです。
こんなに価値があるなら入札にしてみようかな
実は、買手として困るのは、最初は相対形式で話が進んでいたのを、売手がターゲット会社の価値に気づき、
「これならもっと高値で売れるのでは?」
と思って、改めて入札案件に切り替えたりするケースです。
買手側のFAとしては、そうならないように、うまく売手をリードしていくことも大切なポイントです。
アドバイザー(FA)、弁護士・会計士・税理士等専門家の起用
FAはビューコン等で選ばれます。
(詳細は、FAとビューコンについて別記事を書きます)
弁護士・会計士・税理士等の専門家はどのタイミングで起用されるのかといいますと、専門家とひとくくりにしていますが、だいぶ違います。
弁護士
株式譲渡のプロセスでは、売手でも買手のいずれであっても、弁護士は案件の初期段階から関与することが多いです。
売手であれば、売却スキームの法的な問題点の確認が必要ですし、買手であれば第1次意向表明書の簡単なチェック等があったりします。
会計士・税理士
一方で、会計士と税理士はDDのみにて関与というケースがほとんどだと思います。
特に国内の株式譲渡案件では、売手は会計士も税理士も起用しないケースが多いです。
買手も、会計や税務の論点もそんなに多くはないため会計士と税理士はDDのみにフォーカスしてもらうというケースがほとんどです。
ただし、株式譲渡に加えて事業譲渡や会社分割がセットになる案件等、特殊な事情がある場合には、税務まわりの論点整理のために初期段階から会計士と税理士に関与してもらうこともあります。
秘密保持契約書の締結
どのような株式譲渡案件でも、プロセスのはじめに秘密保持契約(NDA= Non-disclosure agreement や CA=Confidentiality Agreementとも言われる)が必要です。
これは、守秘性の高い情報を授受するので、その前提として当然の整理です。
秘密保持契約の種類
実際には、秘密保持契約の締結の種類にはいくつかパターンがあります。
- 秘密保持誓約書(買手のみ記名押印の差し入れ形式)
- 秘密保持契約書(片務:双方が記名押印し、買手のみ秘密保持義務を負うもの)
- 秘密保持契約書(双務:双方が記名押印し、双方が秘密保持義務を負うもの)
秘密保持誓約書
まず、一つ目の秘密保持「誓約」書とは、買手が売手に一方的に書面を差し入れるもので、特に、入札形式の案件で採られることが多いものです。
買手候補が複数社いる入札案件の場合、それぞれの候補先と個別に秘密保持契約を結ぶのは煩雑であり、また、買手からは何ら秘密情報を得ないという整理で、一方的に買手候補にだけ秘密保持義務を課す枠組みとするものです。
売手にとっては、買手が一方的に秘密を保持しますと言ってくれるわけですから、「楽な」パターンです。
秘密保持契約書(片務)
次に、契約書であっても、買手だけが秘密保持義務を負うとする契約もあります。
これは、秘密保持誓約書と後述の双務の秘密保持契約所の間に位置づけられるものだと考えられます。
秘密保持契約書(双務)
最後に、売手と買手候補の双方が秘密保持義務を負う秘密保持契約のパターンもあります。
特に、相対形式の株式譲渡案件や、株式譲渡ではない「統合案件」で用いられるケースが多いです。
株式譲渡案件では、買手候補の立場が強くて、意向表明等の情報につき、売手に秘密保持義務を負わせたい場合に双務の契約となります。
秘密保持契約書の有効期間
時々クライアントから、
「秘密保持契約書の有効期間を何年にすべでしょうか」
と質問されることもあります。
一般的には、2年〜3年としているケースが多いように感じています。
秘密保持契約の実効性を高めるために
近年は日本でもM&Aが活発になり秘密保持義務についても啓蒙が進んだため、闇雲に秘密保持義務を破ろうとすることはほとんどないように感じています。
当事会社でできる工夫・・・誓約書
M&Aの当事会社(売手・買手)では、秘密保持契約書の実効性を高めるために、関与するメンバーから誓約書をとることがあります。
要は、M&A案件を知りましたが、一切他言はしませんし、してしまった場合には相応のペナルティを受けても仕方ありませんと言った内容で署名押印させるものです。
メンバーリスト(ワーキンググループリスト)
また、M&A案件では、誰が案件を知っているのかを管理するために、メンバーリスト(ワーキンググループリスト)を作ります。
メンバーリストとは、
会社担当者、弁護士・会計士・税理士、FAにつき、それぞれの住所・氏名・役職・メールアドレス・電話番号等を一覧表にまとめたものです。
なお、一覧表に載っているもの同士でも、外部と遮断された会議室等の場所以外では案件の話はしないということを徹底させる必要があります(廊下やエレベーターホールでは案件の話はしない)
さいごに
次回以降は、株式譲渡案件の1次プロセスのメインテーマである、プロセスレターやインフォメモ等の実態のところを確認していきます。
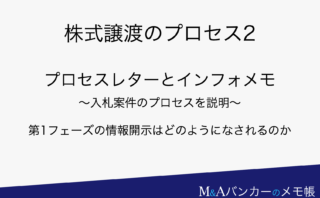
関連する連載記事(全5回)
https://ma-banker.com/process-for-stock-purchase1