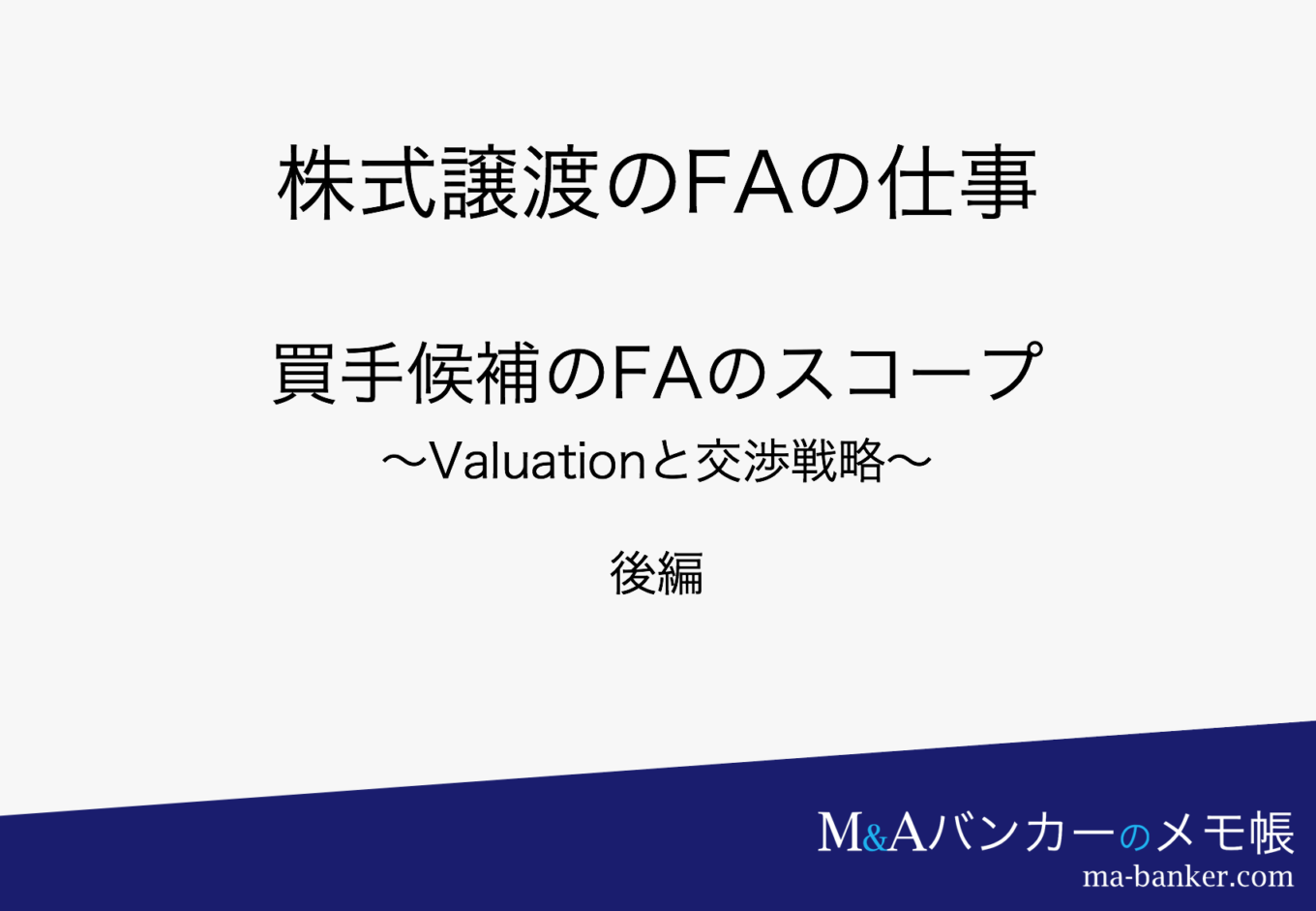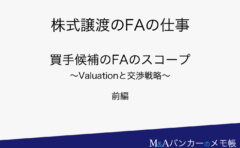前回の記事に引き続き、株式譲渡案件の買手候補のFAのスコープを確認していきましょう。
(前回の記事)
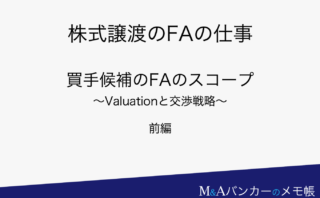
- 対象会社の初期的分析(フェーズ1を想定)
- 買収プロセスのサポート(売手FAの窓口としても機能)
- 買収方針・ストラクチャーに関するアドバイス
- DDのサポート
- Valuation
- 各種契約書等の書面のドキュメンテーションに関するアドバイス
- 交渉に関するアドバイス
- その他案件に関する全般サポート(IR・適時開示、取引所対応、法規制対応)
FAのScope of Work(買手候補編・・・続き)
5.Valuation 〜 買収価額(Offer Price)はどのように決まるのか
Valuationの各手法に関する論点整理は別の記事に譲るとして、ここでは、意向表明書に記載する買収希望価額(Offer Price)をどのように組み立てるのかということをFAが報告するValuation結果も含めて考えてみたいと思います。
DDフェーズに進むために・・・
買手候補としては、DDフェーズに進むためには初期的なValuationの評価レンジ(金額の範囲)の高値でオファーした方がベターであるという議論があります。
実際に、対象会社が魅力的な会社で、買手候補が多数存在するケースは別ですが、一般的なオークションプロセスの傾向としては、DD前と後とではDDで発見されて検出事項を反映させた指し値になるということで、DD後のオファープライスは下がりやすいように感じます。
といっても、DDフェーズに進まなければそもそもそういった金額の交渉戦略も考えようが無いという意味で、とりあえずDDに進むことを第一目的にして初期的なValuation(主に売手が提示するマネジメントケース)を単純に採用して、その金額を第1時意向表明書の金額とするという考え方もあります。
ただし、DD前後であまりにも金額の落差が大きいと売手FAから、どういう前提でそんなに金額を下げたのかを強くトレースされることもありますので、その説明材料は用意しておく必要はあるでしょう(基本的にはDD発見事項を金額に織り込んだとか、事業計画の見立てが保守的になったといった説明になるのかと思います)。
クライアントには無理強いしてはならない
ただし、買手候補によっては、第1フェーズであっても、
「これ以上の金額は出せない」
という感覚を持っていることもあるため、FAとしてはそれを超えてオファーさせるように誘導すべきかどうかは悩みどころです。
買手候補であるクライアントにとって本当にその対象会社の買収に意義があるのであればとりあえず第1フェーズという理由からそれなりに高値を指すことをおすすめもしますが、結局DD後に金額を下げるのであれば、専門家コスト(さらに社内チームの時間)をかける前に撤退するというのも合理的な判断であり、悩ましいところです。
いずれにせよ、Valuation結果そのものよりも買手候補の感覚を大事にして、何度も協議をするとう姿勢が大事だと思います。
繰り返しになりますが、FAとしては、競合入札者の情報やValuationの結果をふまえ、どのあたりが買収可能な安全圏なのかをコメントはするものの、最終決定は買手の意見に従うという気持ちが必要だと思います。といいますのも、FAに求められているのは「M&Aの専門的見地からの助言」ということを忘れてはいけないからです。
買手候補のFAとしては、買収しないと手数料をいただけないので、本音ではジレンマを感じますが、ビジネスは「繰り返しゲーム」でもあるわけで、短期的な自社の利益よりも長期的なクライアントとのWinwinの関係を構築するようにしたいところです。
最終意向表明のオファープライスについて
DD後の最終意向表明書にて提示するオファープライスをどのようにするのかは、買手候補のFAの腕の見せ所です。
要は、競合入札者よりも高ければ勝てますが、無駄に高値にしてもクライアントの負担が増えるだけですし、保守的に低く指し値をして入札に負けてしまえば対象会社を買収することはできません(ついでにFAの成功報酬も貰えません)。
優秀なFAならあらゆる方法で自社のクライアントが勝てるように、但し合理的な範囲内での指し値となるように尽力することになろうかと思います。
なので、仮に最終意向表明段階においても、単に受け身的にValution結果を報告しているだけのFAであれば、それはクライアントにとっては望ましい対応ではないかもしれないという危機感を持った方が良いと思います。
6.各種契約書等の書面のドキュメンテーションに関するアドバイス & 7.交渉に関するアドバイス
買手候補のFAが作成をサポートする書面としては、意向表明書や株式譲渡契約書があります。
まず意向表明書については、プロセスレターの指示を踏まえて、意向表明書の金額・条件をどのように記載するかとかアドバイスする点が多くあります。
特に、他の事例ではどのような記載方法があったのかを問われることも多いため、事例を一般化してあまたに入れておくことが望ましいと思います。
株式譲渡契約書についてもDDの結果を踏まえて、何を表明保証させるべきか、クロージングまでの義務をどうするか、そして何をクロージングの前提条件にすべきかについて、弁護士と共にアドバイスします。
弁護士はどちらかというと法務テクニカルな面での指摘を得意とするため、網羅的にどのような論点があるのかは買手候補のFAが把握しておき、漏れなく契約書に織り込まれているのかをチェックするという観点を持ち続けたいところです。
そういう意味でもDDの時にしっかりと対象会社の状況を把握しておく必要があり、Q&Aシートのやりとりや実務インタビューセッションに同席するジュニアに対しては、適切に重要論点を把握しておくようにお願いしたいところです。
8.その他案件に関する全般サポート(IR・適時開示、取引所対応、法規制対応)
これは売手のFAの時と同じく、要はよろず相談ということです。
買手候補のFAとして、案件に関することなら基本的になんでも受け付けて、必要な場合には専門家の先生と協働して論点解消に努める必要があります。
クライアントとしては、とりあえず何でもFAに投げておけば上手く捌いて回答をくれるという流れができているとやりやすいので、そのように頼っていただけるように案件の潤滑油としての役割もしっかりとこなしていきたいところです。
さいごに
買手候補のFAのスコープについて見ていきましたが、やはり肝は買収金額と条件の交渉戦略について助言することです。
このあたりは案件数といいますか、過去の案件でどれだけ真剣に案件と向き合ってきたのかでどれだけ良いアドバイスができるかが変わってくるように思いますので、毎度の案件を一球入魂の気持ちで取り組みたいところです。