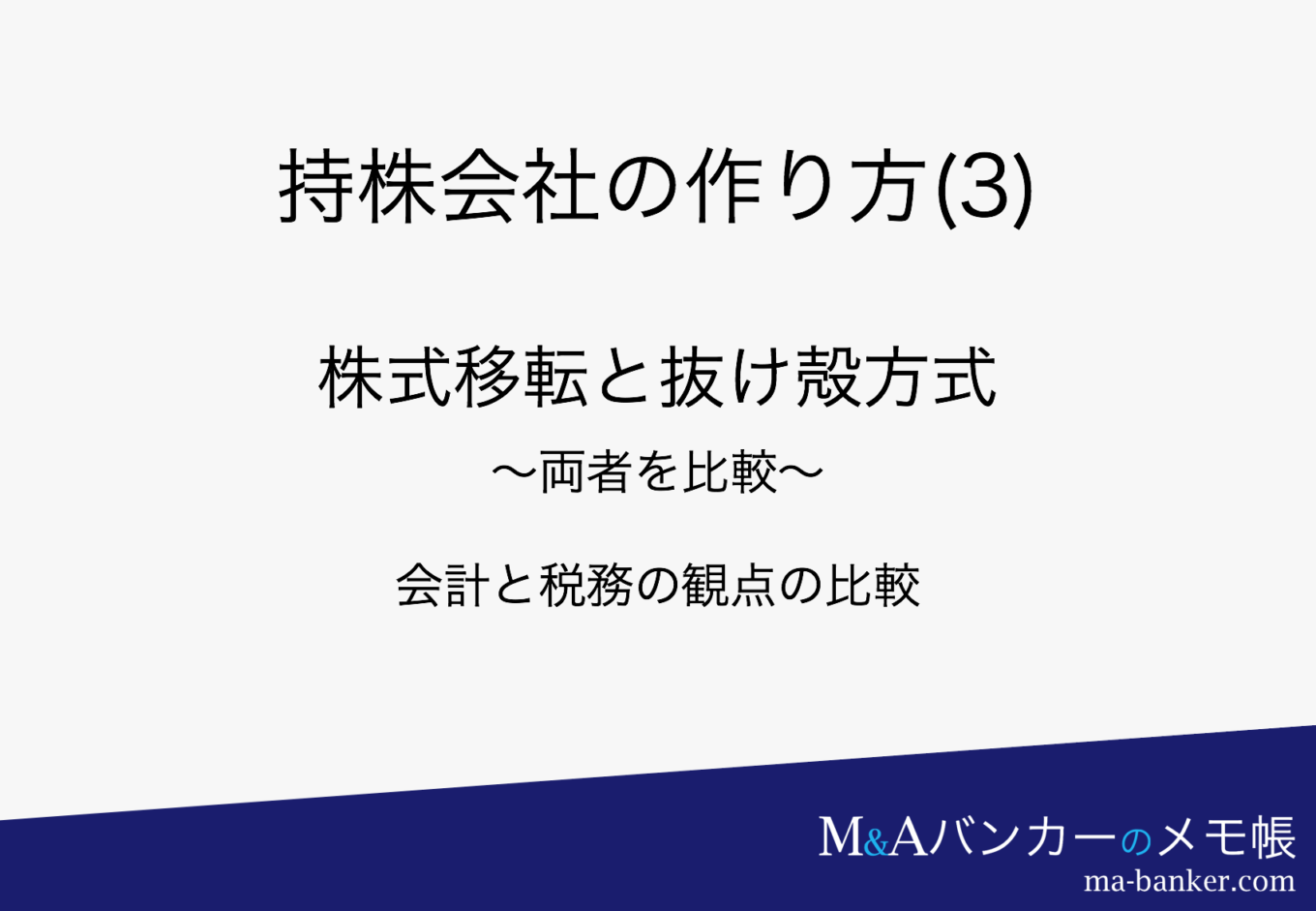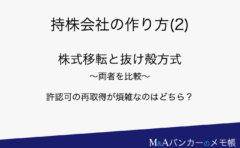今日も前回に引き続き、持株会社の作り方についてみていきます。
(前回の記事)
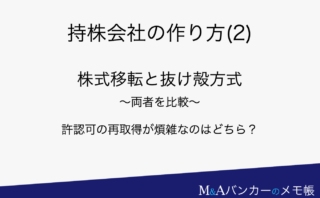
今回は、株式移転と抜け殻方式のそれぞれを比較の残りの部分を見ていきます。
株式移転と抜け殻方式の比較(後半)
まず、比較のポイントを再掲します。前回は3まで確認したので、今回は4つ目の配当原資から見ていきましょう。
- 新設会社によるテクニカル上場
- 許認可等の再取得と契約の引き継ぎ
- 株主・債権者対策
- 配当原資(剰余金問題)
- 税務(特に欠損金の帰属)
それぞれ、ひとつずつ丁寧に見ていきます。
配当原資(剰余金問題)
配当原資(剰余金問題)を理解するためには、株式移転と会社分割の会計処理を確認していく必要があります。
まず、は共同株式移転の会計処理を理解することからはじめましょう。
共同株式移転の単体の会計処理を学ぶ
まず、配当原資(剰余金問題)は配当可能利益に関する論点であり、単体の会計処理についての話題であることに留意して下さい。
たとえば、A社とB社による共同株式移転での新設会社(HD社とする)の設立直後のBSを最も単純化すると次のようになります。
| 【HD社のBS(単体)】 | |
| A社株式 XXX | 株主資本 XXX |
| B社株式 XXX | |
それぞれの金額の求め方は、
に規定されています。
数値例で考えてみる
次のような具体例で考えてみましょう。
【前提】
- A社とB社が株式移転
- A社が取得する方(B社は被取得)
- A社の簿価純資産は500
- B社の簿価純資産は200
- A社の旧株主に発行されたHD社株式総額は800
- B社の旧株主に発行されたHD社株式総額は300
【問題】
上記前提で先ほどのBSの金額を算出せよ
数値例の解き方
簡単そうに見えて案外難しいです。
パーチェス法ということで自然に考えると、A社株式は簿価純資産の500、B社株式はHD社株式総額を充てて300というところまでは自然の流れで算出できると思います。
一方で、貸方の株主資本はどうすれば良いでしょうか。
発行した株式時価総額は合計で1,100ですが、単純にそれを採用するとBSの貸借が合わなくなってしまいます。
さて、「差額はのれん」と単純に処理して良いのでしょうか。
実は、単体でのれんが発生するのは、原則として合併・事業譲渡・会社分割の時だけです(そして、基本的に単体でのれんが出る場合は、税務のれんも一緒に発生する可能性が高いです)。
差額をのれんとする というのは連結のれん(連結調整勘定)のことなので、単体ではそのような考え方はあまり採られません。要は、株式移転直後の会社が単体でのれんを計上するのには違和感があるとなります。
・
・
・
答えを述べますと、実は難しく考えずに、株主資本はA社株式とB社株式の金額の合計で差し支えありません。
| 【HD社のBS(単体)】 | |
| A社株式 500 | 株主資本 800(※1) |
| B社株式 300 | |
| (※1)借方のA社株式とB社株式の単純な和 | |
配当原資(剰余金問題)がなぜ論点になるのか
ここで、そもそもの話の「剰余金問題」というのはこの株主資本800が割り振られる項目に起因します。ポイントは、
ということです。
資本金、資本準備金、その他資本剰余金のいずれかには自由に割り振ることができますが、利益剰余金は増やせないのです。
その他資本剰余金を増加させておけば配当はできますが、それを受け取る株主にとって、少しややこしいことになります。
端的に言うと、会計面では資本の払い戻しになり、税務面では資本の払い戻しの部分と配当の部分に分けられることになります。
つまり、株式移転の場合は配当原資が「その他資本剰余金」になってしまう、ということがポイントなわけです。
抜け殻方式なら利益剰余金が残る
一方、抜け殻方式(会社分割の抜け殻方式)の場合は、持株会社となるもともとは事業会社であった会社の株主資本項目がそのまま残ります。
なので、抜け殻方式ならば、持株会社化の直後から利益剰余金での配当ができるのがメリットといえます。
株式移転直後に子会社が特別配当すると・・・
なお、株式移転の場合も完全子会社になる事業会社の利益剰余金は引き続き残ります。
なので、株式移転直後に完全子会社となったその事業会社から特別配当して、持株会社で受取配当金を認識すれば、利益剰余金が増えるという考え方もあります。
しかし、実務上は基本的にこの考え方は使えないようです。
最終的には持株会社の監査法人との協議になるものの、株式移転後に子会社が獲得した利益剰余金を超過して配当した場合、それは資本の払い戻しであろうとみなされて、持株会社で受取配当金を認識できず、代わりに投資勘定を減額する(BSの入り繰りのみとなる)という考え方があります。
念のため、その会計基準の適用指針を抜粋しておきます。
企業会計基準適用指針第 3 号
その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理
第13項
なお、本質的には支払側の配当の原資(その他資本剰余金又はその他利益剰余金)により、自動的に受取側の会計処理(投資成果の受取又は投資の払戻し)が決定されるわけではない。例えば、以下の場合には、支払側の配当の原資に従って受取側が処理しても、必ずしも投資成果の分配と投資そのものの払戻しを整合的に処理できない。
(1) その他利益剰余金の処分による配当の原資が、投資以後に投資先企業が計上した留保利益の額を超えている場合
税務(特に欠損金の帰属)
最後に税務の観点です。
端的に言うと繰越欠損金の帰属先が一番の論点になります。
欠損金の帰属先は?
欠損金の帰属先は、
- 株式移転:傘下の事業会社
- 抜け殻方式:持株会社(と、傘下の事業会社の片方)
となります。
抜け殻方式(会社分割)では、欠損金を傘下に切り出せず、抜け殻になった持株会社に欠損金が残るというのが原則のようです。
ということで、抜け殻方式で欠損金を残した持株会社において、単体で課税所得がほとんど発生しないと欠損金が使い切れないなんてことになりかねないので注意が必要です。
連結納税制度を採用すれば解決できるかもしれない
連結納税に関する欠損金の使用制限については、制度が刻々と改善しており、現在は最上位の親会社以外の欠損金であっても、一定の要件を満たせば連結欠損金として使えるケースも増えてきております。
ですから、経営統合で持株会社化を検討する場合、税務の観点からは連結納税の導入をあわせて検討するのがベターだと考えております。
さいごに
株式移転と抜け殻方式をみてきましたが、実務上は株式移転の方が好まれるようです。
これは、全事業を分割するという行為が上場会社にとってはかなり困難であるからだと思われます。
関連する連載記事(全3回)
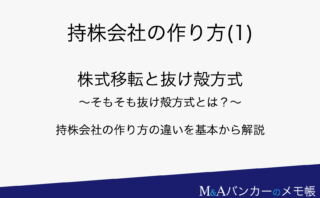
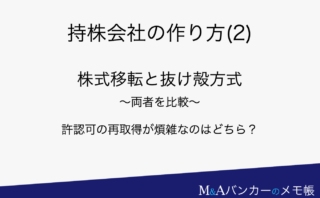
https://ma-banker.com/holding-company3